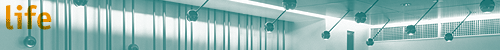
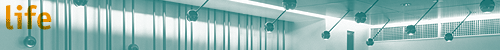
7/16。武蔵野美術大学美術資料図書館展示室で開催されていた『デザイン国際化時代のパイオニア─川上元美・喜多俊之・梅田正徳の椅子デザイン』の最終日閉館一時間前に滑り込み。
それぞれ実に個性的な作風を持つ川上氏、喜多氏、梅田氏だが、1960年代末にイタリアに渡り、当地でデザイナーとしての本格的なキャリアを築いた点は共通している。川上氏はアンジェロ・マンジャロッティ氏の建築事務所に勤務し、梅田氏はA&PGカスティリオーニの事務所を経てエットーレ・ソットサス氏のもとolivettiのコンサルタントデザイナーを務めたとのこと。いやはやため息の出るような華々しい経歴だ。一方、27歳で訪伊した喜多氏は「いちばんいいものを見て、いちばん美味いものを食べて、3ヶ月くらいで帰るつもりだった」(インタビュー映像より)そうなのだが、徐々にイタリア語が分かるようになりつつあった帰国間際の時期にたまたまデザイン事務所のアルキテット(主任デザイナー)の職を得て、以来大阪とヨーロッパを往復しながらデザイン活動を行っているなんともラテンな方。

(写真左:会場入口/写真右:川上氏の作品展示)
その後40年近くものあいだ、いまだ一向に地力の上がらない日本のプロダクトデザイン事情を尻目に、三氏は世界の第一線で活躍しつづけているわけなのだが、私たちにはこれまで三氏の作品を間近に見たり触れたりすることのできる機会はほとんど無かった。プラスティックエイジの代表的作品・『FIORENZA』(1968・川上)も、セビリア万博日本館で使用された『MULTI LINGUAL CHAIR』(1991・喜多)も、夢のようにシュールレアリスティックな『GETSUEN』(1988・梅田)も、雑誌で見たことがあるだけの憧れの椅子だった。唯一、川上氏の名作折りたたみ椅子『TUNE』(当時の製品名は『BLITZ』だった)だけは会社員時代に会議室などでよく使わせてもらった。その機能性とエレガントな佇まいに「これが一流のプロダクトか」と思ったものだ。
新御徒町駅から電車とバスにゆられること2時間弱。ようやくたどり着いた会場には三氏のデザインした椅子・数十脚がゆったりと展示され、見応えのある展覧会となっていた。
残念ながらほとんどの作品は「お手を触れないでください」。でも喜多氏の作品『BEO』、『THEATER SOFA』、『DODO』、そして『WINK』には自由に腰掛けたり動かしたりすることができた。
『WINK』の耳のようなかたちをしたヘッドレストは視界をゆるやかに区切り、まるで即席の個室のような感覚をもたらす。仕事モードでデスクに向かうこともできれば足を伸ばして寝転ぶことも出来る可動性と汎用性にも驚いた。なるほど、これは側に置いておきたくなる椅子だ。ファンシーな外観はまさに確信犯的。今でこそ可動部の多い汎用チェアは少なからずあるが、この椅子が製品化されたのは1980年。カッシーナのベストセラーのひとつであることにも大いに納得。『WINK』の進化形のひとつ、『DODO』(1998)のハイテクチェアぶりにも目を見張った。
他にも1970年にデザインされたという『GRU』、MAGISの代表的製品である折りたたみ椅子『RONDINE』(これが氏の作品だったとは恥ずかしながら初めて知った)など、喜多氏の作品群には見所が多かった。

(写真左:喜多氏の作品展示/写真右:梅田氏の作品展示)
座ることは出来なかったが、花をモチーフにした梅田氏の作品の実物にようやく出会えたことは、バブル末期にデザインを志した中年世代2名にとって実に感慨深い。中でもedraで現在も生産されている『GETSUEN』と『SOSHUN』の凛とした造形とディテールの美しさには思わず背筋がぞくっとするほどの迫力があった。予想外の収穫だったのが、メンフィス(ソットサス氏を中心にミケーレ・デ・ルッキ氏、アンドレア・ブランジ氏、倉俣史朗氏らが参加したクリエーターグループ)第一回展(1981)の象徴とも言える大作『TAWARAYA』の実物を見ることが出来たこと。これはもう号泣ものだった(デザインおたく丸出し)。
また、企業クライアントとの地道なコラボレートの多い川上氏の作品をまとまったかたちで見ることが出来たのも大きな収穫だった。近作の介護チェア『かたらい』やオフィスチェア『CAST』にはどこかでぜひ座ってみたいと思う。
デザイン国際化時代のパイオニア─川上元美・喜多俊之・梅田正徳の椅子デザイン