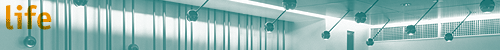
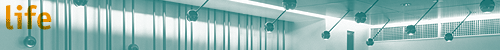
以前『日本のインテリア』のエントリーでも書いたように、インテリアデザイナーの著作物は非常に少ない、と言うかむしろ皆無に近い。それだけに内田繁氏の活動は際立って貴重だ。内田氏個人の著作の中で、最も代表的なものとして挙げられるのがこの4冊。
住まいのインテリア(1986/新潮社)
インテリアと日本人(2000/晶文社)
家具の本(2001/晶文社)
茶室とインテリア(2005/工作舎)

インテリアデザイナーの作品と言うと、どうしても商空間ばかりがクローズアップされる傾向がある。実際には住宅と店舗の両方を手がけるデザイナーは多いが、その住宅の作例を目にする機会はあまり無い。『住まいのインテリア』は内田氏の手がけた住空間と商空間、家具デザインを同列に見ることができることに加え、『インテリア・ワークス』以降に内田氏が試みた自作の分析と、インテリアデザインの源流についての考察の、基となるような記述が散見される点において興味深い本だ。文庫の体裁ながらカラー図版が多く掲載されており、中には篠山紀信氏の撮影したコシノ・ジュンコ邸(1983)の写真も登場する。
『住まいのインテリア』、『インテリア・ワークス』、そして『日本のインテリア』を経た成果は、『インテリアと日本人』で一旦ひとつのかたちにまとめられた。この本の第一章では主に商空間の分野で飛躍的な発展を遂げた日本のインテリアデザインの動向について述べられている。ここで内田氏は、通常ならば建築設計を効率の面から細分化したものとして捉えられるインテリアデザインを、1960年代以降の社会状況を背景に、硬直した近代社会に対して個人の解放を志向するゲリラ的活動の中から生まれた新しいクリエイティブジャンルとして定義し直している点は、極めて重要だ。
続く第二章から第四章にかけては日本人の空間感覚についての考察が行われ、第五章では自作を通じて現代のインテリアデザインに生かされた日本的感性が検証される。特に中盤での、床座・沓脱の習慣から茶室空間へ至る空間感覚の変化と発達を簡潔に解説した内容によって、この本は幅広いデザイン関係者の間で受け入れられた。各パートの関連性は強いものではなく、立て続けに3冊の本に目を通したような読後感がある。
翌年に出版された『家具の本』は、『インテリアと日本人』から第一章と第五章を抜き出し、さらに内田氏の実体験を加味したような内容となっている。長谷部匡氏との対話形式がとられており、文体は平易で読み易い。『家具の本』とはいかにも限定的なタイトルだが、実際には内田氏の60年代から90年代までの全活動を振り返りながら、インテリアデザインとは何だったのかが考察されている。後のデザインの方向性を語る中での「社会とか政治とか経済の仕組みなどといった手の届かないところからいったん離れて、僕の周辺のもっと身近な問題、あるいは手の届く範囲を対象にデザインしていきたい」との言葉は印象深い。
近作の『茶室とインテリア』は、『インテリアと日本人』の中盤(第二章から第四章)充実させたものであると言えるだろう。沓脱、間仕切、装飾、祭祀、色彩などの各章ごとにインテリアデザインと日本人との歴史的な関わりが解説され、それぞれにおいて現代の生活空間との関連性、さらに今後の課題に関する論考が展開されることで、内容は『インテリアと日本人』よりも一層詳細になり、かつ整理されている。文体は「です・ます」調だが、その語り口は簡潔で小気味良い。
『茶室とインテリア』の最後の章にあるこの一節(「精神の機能性」)は、デザインやファインアートと言った概念が西欧から持ち込まれる以前の日本において、インテリアとは芸術の一切を互いに結びつけるものであったことを説明すると同時に、これからのインテリアデザインの行くべき方向についての示唆を含むものだ。
近代は、機能性という言葉を生みました。デザインの要素を分類していくなかで、機能という言葉が強調されたわけです。ものを見る目が失われても、これは使いにくい、座りにくいといったように、機能性についてだけは判断できます。ところが、ものに機能があるのは当然です。用途性ということでは、光琳の「杜若図屏風」も、日本では道具です。春の座敷を飾るための重要な道具でした。
芸術とデザインを分類するときに、デザインには機能が不可欠で、芸術には機能はいらない、といわれます。しかし芸術に機能がまったくないわけではありません。日本的な考え方では、「杜若図屏風」も生活に役に立ちます。だから機能という考え方も、精神にまで及んだ瞬間から、より豊かなものになるはずです。(内田繁『茶室とインテリア』より)
内田繁(Creators Channel)