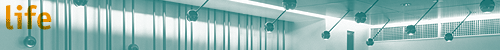
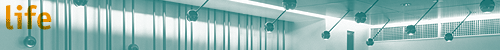
珈琲店巡りは私たちにとって重要な趣味のひとつ。でも珈琲の味そのものを追求することについてはあくまで素人にとどまっておこうと思う。私たちの前に置かれた黒い液体には、コーヒーの木を育て豆を採取するところから始まり、様々な行程と長い長い道のりが濃縮されている。珈琲のプロ、あるいは通ともなると、その行程の全てとは行かないまでも、要所に目を光らせることはおそらく当然だろう。私たちには到底そんな根性は無い。その道を邁進する修験の人々に最大限の尊敬を払い、珠玉の珈琲を分けていただくために謹んでその扉を叩くのだ。

プロと素人を分ける境目を、私たちは「焙煎」という行程に置く。やったことはないが、焙煎はとにかく難しく、奥深そうなものに思える。珈琲の味の大方は焙煎で決まる、と言うのは珈琲好きにとって基本中の基本の常識だが、こうした常識が国内に定着するまでには多くの人々の努力と研鑽を要した。そうした功労者の中でも特に襟立博保(1907-75/『リヒト』、『なんち』など)、関口一郎(1914-/『ランブル』)、田口護(1938-/『バッハ』)、標交紀(1940-/『もか』)の4氏の存在は伝説的だ。その足跡は『コーヒーに憑かれた男たち』(2005/写真右下)に詳しい。
4氏のアプローチはそれぞれに個性的で、またそれぞれに凄まじい。襟立氏は大阪に店を開いては潰しながら、岩のような頑固さで理想の珈琲を提供し続ける“怒る喫茶店”の主だった。徹底した合理主義者でありオールドビーン研究者である関口氏は、自宅に5トンの生豆を貯蔵可能なエージングルームを持つと言う。田口氏は“よいコーヒー”の条件をシンプルに明文化し、アメリカンやなんとかマウンテンを盲目的に信奉する業界の通念を否定し尽くした。
襟立氏を師と仰ぐ標氏の珈琲に向かう姿は求道者そのものだ。『コーヒーに憑かれた男たち』に記された様々な逸話は時に可笑しく、時に涙ぐましく心に迫る。“ダイヤモンドのコーヒー”を探してのヨーロッパ歴訪については、氏の著書『咖啡の旅』(1983/写真左)により詳しい。旅の終盤、遂に一点の非の打ち所無く焙煎された珈琲豆に遭遇した氏が、結果「完全過ぎる味は、完全ではない」と気付くエピソードには実に考えさせられものがある。また、同じく標氏の著書である『苦味礼賛』(1984/写真左上)は『もか』開業からの変遷と襟立氏との交流、そして珈琲に対する氏の熱い思いが簡潔な文体で書き綴られた内容。読めばあっと言う間の小さな書物ながら、上記の両書を補うものとして興味深い。
『コーヒーに憑かれた男たち』の締めくくりは、一見悲観的なトーンに覆われている。4氏の数十年に渡る活動を経た今も「世の中の人間の九十九%は、うまいコーヒーがどんなものかを知らない」という現実は動かし難い。「いい豆には必ず匂い立つような気品が感じられる」と関口氏は語り、「コーヒーも最後は“品格”のあるなしで決まってしまう」と標氏は話す。そんな哲学的な珈琲は、所詮ごく限られた好事家のためのものに過ぎないのかもしれない。しかし、1800年頃に発明されヨーロッパで一時隆盛を極めたドリップコーヒーを、いま現在、最も美味しくいただけるのが、他でもない日本の自家焙煎珈琲店であることもまた事実なのだ。
私たちにはこうした事柄の持つ本質が、自身の携わるデザインの現状に大部分重なり合って見える。一杯の珈琲が語りかける言葉に静かに耳を傾けながら、私たちはデザインの未来を思う。
良質な珈琲と良質なデザイン。
先々まで生きながらえるのは果たしてどちらだろうか。
コーヒーに憑かれた男たち/嶋中労著/中央公論新社/2005
咖啡の旅/しめぎ交紀著/みづほ書房/1983
苦味礼賛/標交紀著/いなほ書房/1984